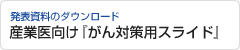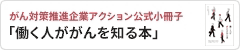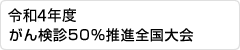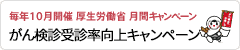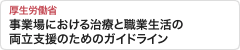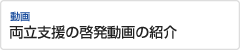※株式会社法研からの情報提供により掲載しております。
以下の掲載については、本事業において内容を保証しているものではありません。
以下の掲載については、本事業において内容を保証しているものではありません。
大腸がんの化学療法は、手術ではがんを取り切れない進行がんや再発がん、転移がある場合、術後に再発する可能性がある場合などに行われます。最近、3種類の分子標的治療薬が承認され、治療の選択肢が一気に広がりました。
再発・転移がんには分子標的治療薬の併用も
化学療法とは、薬を使ってがん細胞を死滅させたり増殖を抑える治療法です。薬だけでがんを治すことはできませんが、小さくして生存期間を延ばすなどの効果があります。
大腸がんで化学療法が治療の中心になるのはⅣ期で、手術ではがんを完全に切除できない進行がんや再発がん、ほかの臓器に転移がある場合です。一般的な方法は、下記のような従来の抗がん剤を組み合わせる3剤併用療法です。再発した場合や転移がある場合は、これに最近使えるようになった3種類の分子標的治療薬(ベバシズマブ、セツキシマブ、パニツムマブ)から1つを加えることもあります。分子標的治療薬は正常な細胞には作用せず、がん細胞だけを攻撃する薬です。
大腸がんで化学療法が治療の中心になるのはⅣ期で、手術ではがんを完全に切除できない進行がんや再発がん、ほかの臓器に転移がある場合です。一般的な方法は、下記のような従来の抗がん剤を組み合わせる3剤併用療法です。再発した場合や転移がある場合は、これに最近使えるようになった3種類の分子標的治療薬(ベバシズマブ、セツキシマブ、パニツムマブ)から1つを加えることもあります。分子標的治療薬は正常な細胞には作用せず、がん細胞だけを攻撃する薬です。
● 抗がん剤を使うとき
【進行がん・再発がん】
Ⅳ期の進行がんや再発がんでほかの臓器に転移があるなど手術ではがんを完全に取り除けないとき。
【術前補助化学療法】
進行した直腸がんに対し、手術の前に薬を使ってがんを縮小し、肛門機能温存術が期待できるとき。
【術後補助化学療法】
リンパ節への転移があるⅢ期の進行がんを中心に、術後の再発防止を目的とするとき。
● 抗がん剤の組み合わせ
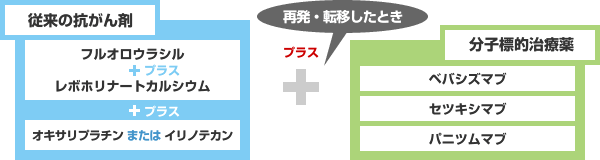
治療後も定期的に検査が必要
大腸がんは再発や転移が比較的少ないがんですが、再発は約17%にみられ、その約95%は術後5年以内におこっています。大腸に再びがんができる「局所再発」は直腸がんに多く、ほかの臓器にがんが発生する「遠隔転移」はどちらにもみられます。転移しやすい臓器は肝臓や肺です。
再発や転移があっても、そのがんを手術で完全に取り除くことができれば治すことができます。そのために、術後5年間は定期的な検査を受ける必要があります。血液検査を2~3カ月に1回、CT検査を半年~1年に1回、大腸内視鏡検査は術後1年目に受け、次は3~5年後というのが標準的なスケジュールです。
骨転移や手術が難しい局所再発には、放射線療法が行われることもあります。
再発や転移があっても、そのがんを手術で完全に取り除くことができれば治すことができます。そのために、術後5年間は定期的な検査を受ける必要があります。血液検査を2~3カ月に1回、CT検査を半年~1年に1回、大腸内視鏡検査は術後1年目に受け、次は3~5年後というのが標準的なスケジュールです。
骨転移や手術が難しい局所再発には、放射線療法が行われることもあります。
情報提供元:法研
本ページの掲載内容は、2011年時点の情報です。
本ページの掲載内容は、2011年時点の情報です。