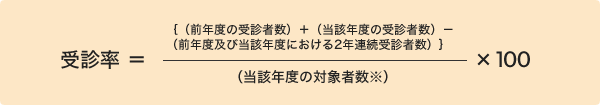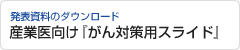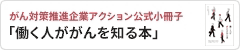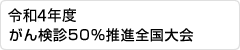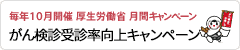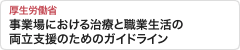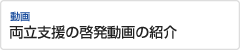がん検診は、がんを早期に発見・治療することにより、がんによる死亡を予防する目的で行なわれます。
がん検診の効果を科学的に評価した上で、効果があると証明されたものを実施していくのが国際標準です。
がんの部位や検査の種類によって有効性は異なりますが、下記の表以外の検診方法は、効果が不明もしくは効果がないといえる検診といってよいでしょう。
がん検診の効果を科学的に評価した上で、効果があると証明されたものを実施していくのが国際標準です。
がんの部位や検査の種類によって有効性は異なりますが、下記の表以外の検診方法は、効果が不明もしくは効果がないといえる検診といってよいでしょう。
がん検診のガイドラインと検診受診率の算出方法
がん検診によりがんによる死亡を減少させるためには、有効な検診を正しく実施しなければなりません。有効性評価に基づくがん検診のガイドラインと検診率受診率の算出方法に沿ったがん検診の推進をお願いします。
■ 検診項目[胃がん、肺がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん]
※「有効性評価に基づくがん検診ガイドライン」より引用・改変
| 対象 部位 |
対象者 | 検診の方法 | 判定結果※1 | 実施体制別の推奨 | ||
| 死亡率減少 効果の 証拠※2 |
不利益の 大きさ※3,※4 |
対策型検診 (住民検診等) |
任意型検診 (人間ドック等) |
|||
| 胃 | 50歳 以上 男女 |
胃X線検査 | あり | 利益より小 | 推奨する | 推奨する |
| 胃内視鏡検査 | あり | 利益より小 | 推奨する | 推奨する | ||
| ペプシノゲン法 | 不十分 | 利益より小 | 推奨しない | 個人の判断に より実施可※6 |
||
| ヘリコバクター ピロリ抗体 |
不十分 | 利益より小 | 推奨しない | 個人の判断に より実施可※6 |
||
| 肺 | 40歳 以上 男女 |
非高危険群に対する 胸部X線検査、 及び 高危険群に対する 胸部X線検査 と喀痰細胞診併用法 |
あり | 利益より小 | 推奨する※9 | 推奨する |
| 低線量CT | 不十分 | 利益より大の 可能性 |
推奨しない※5 | 個人の判断に より実施可※6 |
||
| 大 腸 |
40歳 以上 男女 |
便潜血検査 | あり | 利益より小 | 推奨する※7 | 推奨する |
| S状結腸内視鏡検査 | あり | 利益と同等の 可能性 |
推奨しない | 推奨する | ||
| S状結腸内視鏡検査 +便潜血検査 |
あり | 利益と同等の 可能性 |
推奨しない | 実施可※8 | ||
| 全大腸内視鏡検査 | あり | 利益と同等の 可能性 |
推奨しない | 実施可※8 | ||
| 注腸X線検査 | あり | 利益と同等の 可能性 |
推奨しない | 実施可※8 | ||
| 直腸指診 |
なし | — | 推奨しない | 推奨しない | ||
| 子 宮 頸 部 |
20歳 以上 女 |
細胞診(従来法) | あり | 利益より小 | 推奨する | 推奨する |
| 細胞診(液状検体法) | あり | 利益より小 | 推奨する | 推奨する | ||
| HPV検査を含む方法※10 | 不十分 | 利益より大の 可能性 |
推奨しない※5 | 個人の判断に より実施可※6 |
||
| 乳 房 |
40-74 歳女 |
マンモグラフィ単独法 | あり | 利益より小 | 推奨する | 推奨する |
| 40-64 歳女 |
マンモグラフィと視触診の 併用法 |
あり | 利益より小 | 推奨する | 推奨する | |
| 40歳 未満女 |
マンモグラフィ単独法及び マンモグラフィと視触診の併用法 |
不十分 | 利益より大の 可能性 |
推奨しない※5 | 個人の判断に より実施可※6 |
|
| 全年齢 女 |
視触診単独法 | 不十分 | 利益より大の 可能性 |
推奨しない※5 | 個人の判断に より実施可※6 |
|
| 超音波検査 (単独法・マンモグラフィ併用法) |
不十分 | 利益より大の 可能性 |
推奨しない※5 | 個人の判断に より実施可※6 |
||
※1 死亡率減少効果及び不利益に関する根拠の詳細は各種ガイドラインを参照。
※2 死亡率減少効果の有無を判断する証拠が不十分と判定された検診の実施は、
有効性評価を目的とした研究を行う場合に限定することが望ましい。
※3 がん検診の不利益とは、偽陰性や偽陽性だけではなく、病気がある場合でも必ずしも必要ではない精密検査が行われる
ことや、精神的不安、本来必要としない医療費が追加となることなども含む。
また、たとえがんであっても精密検査や治療を受けた結果、予期できない重度の合併症が生じたり過剰診断にあたる
場合も不利益とする。
ただし、検査による医療事故や過誤そのものは不利益に入らない。
※4 がん検診の利益(死亡率減少効果)に比べ、不利益がどの程度の大きさかを比べる。
※5 死亡率減少効果の有無を判断する証拠が不十分であるため、対策型検診として実施することは勧められない。
※6 がん検診提供者は死亡率減少効果が証明されていないこと、及び当該検診による不利益について十分説明する責任を有する。
任意型検診として実施する場合には、現時点では効果が不明で、
効果の有無が明らかになるにはまだ時間を要する状況にあることと不利益について十分説明する必要がある。
その説明に基づく個人の判断による受診は妨げない。
※7 化学法に比べて免疫法は感度・特異度ともに同等以上で、
受診者の食事・薬制限を必要としないことから便潜血検査は免疫法が望ましい。
※8 安全性を確保するとともに、不利益について十分説明する必要がある。
※9 死亡率減少効果を認めるのは、二重読影、比較読影などを含む標準的な方法を行った場合に限定される。
標準的な方法が行われていない場合には、死亡率減少効果の根拠があるとは言えず、肺がん検診としては勧められない。
また、事前に不利益に関する十分な説明が必要である。
※10 HPV検査を含む方法にはHPV検査単独・HPV検査と細胞診の同時併用法・HPV検査陽性者への細胞診トリアージ法がある。
細胞診によるスクリーニング後にトリアージとして行うHPV検査は検診ではなく、
臨床診断として取り扱われているため本ガイドラインの対象には含まれない。
任意型検診において、特に若年者にHPV検査(単独法)あるいはHPV検査と細胞診の同時併用法を行う場合、
若年者には一過性の感染HPV感染率が高いため、慎重な対応が必要である。
※2 死亡率減少効果の有無を判断する証拠が不十分と判定された検診の実施は、
有効性評価を目的とした研究を行う場合に限定することが望ましい。
※3 がん検診の不利益とは、偽陰性や偽陽性だけではなく、病気がある場合でも必ずしも必要ではない精密検査が行われる
ことや、精神的不安、本来必要としない医療費が追加となることなども含む。
また、たとえがんであっても精密検査や治療を受けた結果、予期できない重度の合併症が生じたり過剰診断にあたる
場合も不利益とする。
ただし、検査による医療事故や過誤そのものは不利益に入らない。
※4 がん検診の利益(死亡率減少効果)に比べ、不利益がどの程度の大きさかを比べる。
※5 死亡率減少効果の有無を判断する証拠が不十分であるため、対策型検診として実施することは勧められない。
※6 がん検診提供者は死亡率減少効果が証明されていないこと、及び当該検診による不利益について十分説明する責任を有する。
任意型検診として実施する場合には、現時点では効果が不明で、
効果の有無が明らかになるにはまだ時間を要する状況にあることと不利益について十分説明する必要がある。
その説明に基づく個人の判断による受診は妨げない。
※7 化学法に比べて免疫法は感度・特異度ともに同等以上で、
受診者の食事・薬制限を必要としないことから便潜血検査は免疫法が望ましい。
※8 安全性を確保するとともに、不利益について十分説明する必要がある。
※9 死亡率減少効果を認めるのは、二重読影、比較読影などを含む標準的な方法を行った場合に限定される。
標準的な方法が行われていない場合には、死亡率減少効果の根拠があるとは言えず、肺がん検診としては勧められない。
また、事前に不利益に関する十分な説明が必要である。
※10 HPV検査を含む方法にはHPV検査単独・HPV検査と細胞診の同時併用法・HPV検査陽性者への細胞診トリアージ法がある。
細胞診によるスクリーニング後にトリアージとして行うHPV検査は検診ではなく、
臨床診断として取り扱われているため本ガイドラインの対象には含まれない。
任意型検診において、特に若年者にHPV検査(単独法)あるいはHPV検査と細胞診の同時併用法を行う場合、
若年者には一過性の感染HPV感染率が高いため、慎重な対応が必要である。
がん検診受診率の算出方法
【実施回数】
がん検診は、原則として一人につき年1回行ってください。
ただし、子宮頸がん検診及び乳がん検診については、原則として2年に1回行い、前年度受診しなかった方に対しては、積極的に受診勧奨をしてください。また、受診機会は、子宮頸がん検診及び乳がん検診についても、必ず毎年設けてください。
受診率は、以下の算定式により算定してください。
がん検診は、原則として一人につき年1回行ってください。
ただし、子宮頸がん検診及び乳がん検診については、原則として2年に1回行い、前年度受診しなかった方に対しては、積極的に受診勧奨をしてください。また、受診機会は、子宮頸がん検診及び乳がん検診についても、必ず毎年設けてください。
受診率は、以下の算定式により算定してください。
▼ 胃がん・肺がん・大腸がん
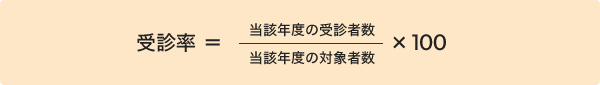
▼ 子宮頸がん・乳がん ※対象者数は、年1回行うがん検診の場合と同様の考え方で算定してください。