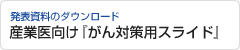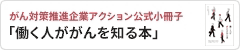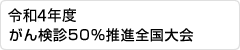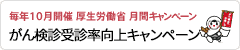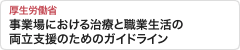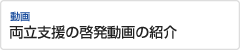「日立ハッピーヘルシープログラム」を中心とした健康増進事業の展開
日立健康保険組合では、肥満解消等社員の健康増進を促すために、「日立けんぽ・はっぴー・へるしー・らんど」というWEBページを公開しています。その中で、「日立ハッピーヘルシープログラム」として、ウォーキングプログラムや、はらすまライト、禁煙サポートプログラムを公開しています。
ウォーキングプログラムでは、多機能歩数計とパソコンを利用し、多機能歩数計から得られた歩数データをWEBに登録すると、歩いた分、WEB上のコースをキャラクターが進んでいきます。
ウォーキングプログラムでは、多機能歩数計とパソコンを利用し、多機能歩数計から得られた歩数データをWEBに登録すると、歩いた分、WEB上のコースをキャラクターが進んでいきます。

▲日立ハッピーヘルシープログラム
ウォーキングプログラム等、WEB上で色々なプログラムを楽しむことができる
ウォーキングプログラム等、WEB上で色々なプログラムを楽しむことができる
コースは、全4種類あり、全コースを制覇すると意気込む加入者も見られます。さらに、ランキング機能もあり、コースランキングやグループ別ランキング等各種ランキングの確認ができ、仲間同士で競い合って、どんどん歩く距離を増やしていっている加入者もおります。このウォーキングプログラムは、2万歩で1枚ずつビスケットが取得でき、取得したビスケットは年度末に集計し、WFP国連世界食糧計画の学校給食プログラムに寄付も行っています。
はらすまライトとは、1日2回、朝と晩に体重の変化を記録しながら、90日で5%の体重減をめざすダイエットプログラムのインターネット版です。
禁煙サポートプログラムとは、インターネットを利用した禁煙セルフプログラムで、WEB上の禁煙日記や禁煙カレンダーを活用し、プログラムに参加している仲間と一緒に禁煙に取り組むことができるものです。このように、インターネットを通じて、健康増進のサポート機能を提供しています。
はらすまライトとは、1日2回、朝と晩に体重の変化を記録しながら、90日で5%の体重減をめざすダイエットプログラムのインターネット版です。
禁煙サポートプログラムとは、インターネットを利用した禁煙セルフプログラムで、WEB上の禁煙日記や禁煙カレンダーを活用し、プログラムに参加している仲間と一緒に禁煙に取り組むことができるものです。このように、インターネットを通じて、健康増進のサポート機能を提供しています。
女性家族の受診率向上として新たな健診メニュー(レディース健診)設立と個別の受診勧奨
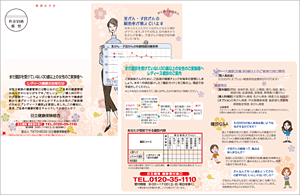
▲女性家族向けDM
ハガキを利用し、できるだけ見やすく工夫している
ハガキを利用し、できるだけ見やすく工夫している
2008年度に日立健保組合の新生物に関する医療費(家族)を確認したところ、その他悪性新生物を除いた件数上位3種類のがん(乳がん・大腸がん・胃がん)が全体に占める割合は、件数ベースでは26.4%、金額ベースでは27.1%と、約3割を占めていました。さらに、年齢別に確認してみると、乳がんは30代前半から高齢になるに従って徐々に増加傾向にあり、30歳~64歳までの年齢層で、乳がんの件数が1位でした。また、50歳後半から胃がん、大腸がんの件数が増え始め、65歳~74歳までの年齢層で、大腸がんの件数が1位、胃がんの件数が2位でした。特に、乳がんについては、医療費が多いにもかかわらず、乳がん検診はあまり受診されておらず、受診率が低い若年層の女性社員・家族の受診率向上を図る必要がありました。
そのため、まずは、30歳以上の女性家族を対象に、法定項目(高確法及び労働安全衛生法)に、女性特有の疾患を対象としたがん検診(乳がん・子宮がん)と、医療費件数が比較的に若年層で高くなっているがん検診(大腸がん)をセットにし、「日立健保レディース健診」として、健診受診者にとって魅力ある健診メニューを作成し提供することにしました。さらに、機関誌等で制度変更案内と受診促進・情報提供を継続的に実施するとともに、DM送付と電話による受診勧奨を行っております。DMとしてハガキを使用し、できるだけ見るものを少なくして、見やすく工夫しています。これらに加え、コールセンターによる未受診者への受診勧奨も行っております。
その結果、2010年度には、レディース健診受診者のうち、73.8%を30~34歳の若年層が占めるようになりました。この年度は、レディース健診受診者のうち68.9%が前年度未受診者でしたので、若年層の受診推進に非常に有効であったと言えます。しかしながら、まだ受診率は低い水準にあるため、引き続き、勧奨等を通じて、受診率向上に努める必要があります。
その結果、2010年度には、レディース健診受診者のうち、73.8%を30~34歳の若年層が占めるようになりました。この年度は、レディース健診受診者のうち68.9%が前年度未受診者でしたので、若年層の受診推進に非常に有効であったと言えます。しかしながら、まだ受診率は低い水準にあるため、引き続き、勧奨等を通じて、受診率向上に努める必要があります。