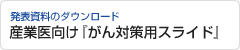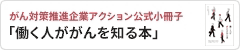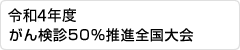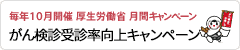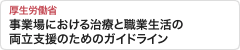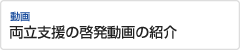検診受診率を高めるポイントは、「受けやすさ=受診環境」
従業員の集中する東京・神奈川の京浜地区健診は、平成24年度までは自社の健康管理センターで健康診断を実施していたのですが、平成25年からは健診後の事後フォローに注力すべく自社での健診はやめ、地域の3つの健診機関での実施に変えました。 それまでは、婦人科がん検診は、別の健診機関に休みをとって行ってもらっていましたが、定期検診と同時に業務内でワンストップで受診ができ、利用者の利便性が向上しました。その結果、変更した年には京浜地区の乳がん検診受診率は、47%→80%、若年の子宮がん検診受診率は17%→55%と大幅に伸びました。
一方、婦人科検診は従来からの健保が厳選した婦人科専門外来でしっかり受けたいというニーズもあったので、それも残し一定の継続受診者がありました。 また、扶養家族ですが、主婦が多く健保組合として家族検診は女性の健康支援の一環と考えています。家族健診にも、婦人科検診を加えたネットワーク健診の仕組を導入し、利便性の向上により、検診受診率16%→55%と受診率アップができました。

社内を巻き込み、粘り強いコミュニケーションで受診勧奨
当初は、身近な社内の健康管理センターで定期検診が受けられたのに、外部で受診するは面倒だと受け取られ、検診の予約がなかなか進みませんでした。その抵抗感を解消してもらうために、現場で泥臭い対策を地道に行った経緯があります。単にシステムを変えて終わりだけでなく、私たちが従業員の健康を守るため、社内の共感者を得て検診の意義を魂をこめて伝え、愚直に繰り返しやり抜く、その姿勢こそが結果に結びつくではないかと考えています。
傾向と対策として、どの部署の検診受診率が低いのかを調べなぜ低いかを考え、低いところには各部署の上長の協力を得て健康管理センターの医療職が直接出向いて、検診の重要性を伝えました。㈱ポーラは訪問販売を主体とした会社ですが、検診でも営業をやったわけです。具体的には朝礼や会議の前の時間を10分ほど割いてもらい、新しい検診の優れた点や、申込方法を説明し、併せて特に婦人科は敷居が高いと思われている中なぜ検診が大切か、また丁寧に各施設の情報を、それも前向きな良い特徴を伝え、「受けなさい」ではなく「私はどこで受けようかな。」と感じてもらえるよう情報発信を続けました。それには、検診に関わる担当者が集団で勉強し受験した「女性の健康検定」「ピンクリボンアドバイザー認定試験」の知識や、その気になってもらうための動機づけ、ソーシャルマーケティングの考えも応用し、プッシュ営業で仕込みました。
また、人事部からのアプローチもありました。人事担当役員、健康管理センター所長(産業医)、労務担当課長連名で、検診の予約を取っていない人の上司に直接検診受診を勧めるよう連絡がいくようにし、また上司が健康診断を受けない場合には役員の方から「就業規則違反」となる旨のメールで勧奨をしました。 館内放送・朝礼での繰り返し、ポスター(施設の情報が掲載してある名刺サイズメモ付)の掲示、また女性の健康セミナー、ライフステージ別女性の健康啓蒙冊子配布など、考えられること全てをやり、「①婦人科のがんは早期発見で助かるし赤ちゃんも産める」「②でも早期がんは自覚症状がない」「③自覚症状がないときに受けるのが検診」という基本的なことをメッセージとして伝え続けました。