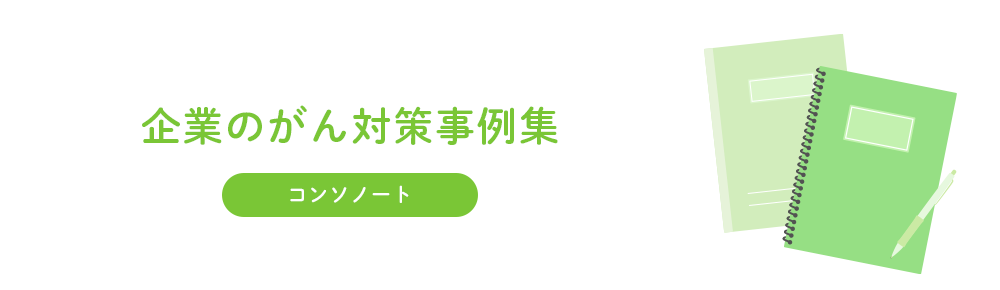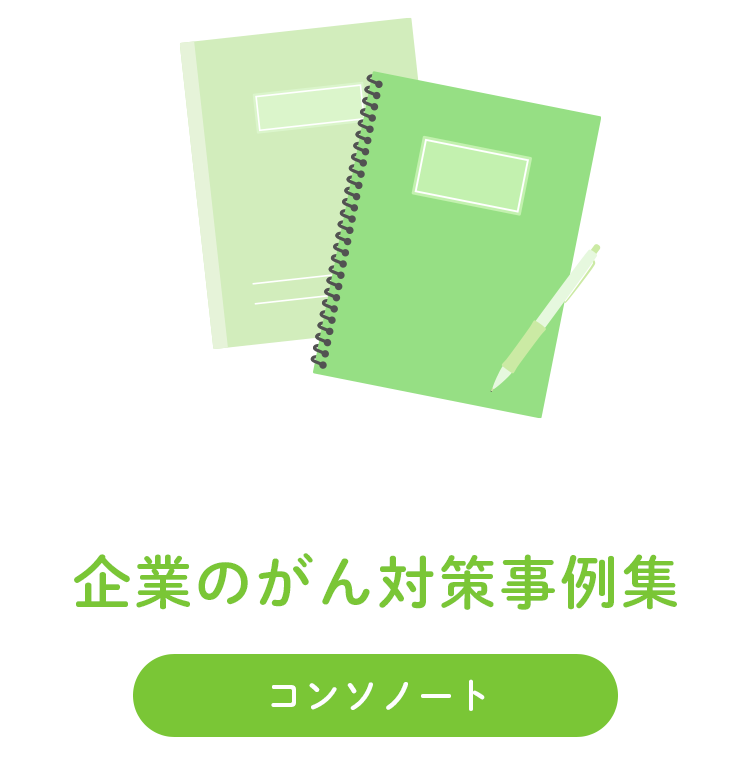パートナー企業・団体コンソノート
能力と個性を十分に発揮できる就労を
100%のがん検診受診と両立できる風土づくりを目指して
野村證券株式会社

水野 晶子 氏(人事業務部厚生課ヘルスサポートグループ長)
高野 真理子 氏(健康管理センター健康相談室 保健師)
野村グループ健康経営キャラクター「ノマトちゃん」(写真中央)
memo
2019年度のがん対策推進企業アクション厚生労働大臣賞を受賞したのが野村證券株式会社です。
従業員数約1万5000人、男女比は約6:4、平均年齢は約40歳。言わずと知れた証券界の大企業です。野村證券の2019年度の健康診断(人間ドック含む)の受診率は、なんと99.4%という限りなく100%に近い数字、2020年度は100%を目指すといいます。そのほか、治療と就労の両立支援にも力を入れており、社員が心身ともに健康で輝いて働ける環境を目指しています。
今回は、水野晶子氏(人事業務部厚生課ヘルスサポートグループ長)、河野和絵氏(人事業務部厚生課ヘルスサポートG)、高野真理子氏(健康管理センター健康相談室 保健師)の3名に、野村證券のがん対策についてお話しを伺いました。
--野村證券は昨年度に、このがん対策推進企業アクションの「厚生労働大臣賞」を受賞されています。がん対策は、早期発見・早期治療がとても有効だといわれており、がん検診の受診が重要です。そんな中で野村證券は、2019年度の健康診断受診率(人間ドック含む)が99.4%という数値でした。ほぼ100%と言っても過言ではない数値ですが、この素晴らしい受診率は、どうやって達成されたのでしょうか?
ありがとうございます。理由としては3つのことが考えられます。
1つ目は、トップダウンでの健康経営の推進です。働き方改革と健康経営推進の取り組みを「Nomura Work Style Innovation(ノムラ・ワークスタイル・イノベーション)」として、多様な人材がその能力を発揮し活躍することができるよう環境整備をすすめています。健康経営推進最高責任者(Chief Health Officer)のもと、グループ各社人事担当役員、人事、産業医、健康保険組合で構成される「健康経営推進協議会」を定期的に開催しています。社員の健康課題の把握や、施策の立案及び実行、結果検証を組織として一貫して行う中で、積極的に健康診断の受診を進めています。
2つ目は、社員の健康管理を行うヘルスサポートグループのメンバーが、積極的に受診勧奨を行っています。まずは直属の上司から受診勧奨をしてもらい、それでも受診しない場合はヘルスサポートグループのメンバーが、直接個別に受診を促します。
3つ目は、インセンティブです。年度内の早い時期に受診することで、健保から健康ポイントが付与され、そのポイントはAmazonの買い物などで使えます。また、4〜12月の間に人間ドックを受診すれば、その日は人間ドック休暇として、有給休暇とは別に特別休暇を付与しており、約7割の社員が利用しています。さらに、再検査が必要になった場合は二次検査休暇を取得することができ、現在は社員の1割程度が利用しています。
以前はどうしても健診を先送りにされがちで、年度末に受診が集中し、そのために保健指導が翌年度に繰り越されて対策が遅くなってしまう問題がありました。現在では95%の社員が12月までに受診するようになり、受診後の対応がスピーディに行えるようになりました。
--人間ドックで受けられるがん検診の種類は、どのようなものでしょうか?
胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんが受けられます。
人間ドックは30歳以上が対象ですが、子宮頸がん検診については、本年度より29歳以下の社員も健康診断時に受診できるようにしました。費用は全額健保負担で、20代女性が抵抗なく受けることができるよう、案内時にリーフレットを付けて受診率向上に役立てています。また、人間ドックは健保が契約している全国の医療機関で、本人が好きな日時に受けることができます。
--社員向けにがんに関するセミナーや勉強会などは開催されていますか?
社内のボランティアチームが、がんに関するセミナーを本社で開催したり、医療職が女性の健康についての話をしたりしています。これらは適宜オンライン配信を行っているので、全国の支店から社員が見ることができます。今後はイベントもオンライン対応していければいいと思います。
社員の健康・運動という面からは、健保からのスポーツクラブの補助に加えて、専門家が職場を訪問して生活習慣病についての講演や腰痛体操を教えたりしています。
また、社内に健康経営プラットフォーム「WellGo」(歩数、食事、睡眠などのライフログの他、健診結果などを一元管理できるシステム)を導入しており、登録(自分の携帯などと連携)すれば歩数などの健康情報を管理することができるので、部署ごとで歩数を競い合うなどしています。昨年11月には、全社員の1日平均歩数が7,000歩を達成した場合、1日あたり1万円が「特定非営利活動法人TABLE FOR TWO International」へ寄付されるイベントを行い、開発途上国の給食支援のために30万円の寄付を行いました。

--今後、定年の延長や女性の活躍の場がさらに広がると、がんを治療しながらの就労が大きな問題となりますが、両立支援はどのようにお考えですか?
社員であれば誰でも健康相談室の保健師や看護師に相談できます。コロナ禍の前は、実際にお会いして相談や指導をさせていただくこともありましたが、現在は電話やメール、オンライン面談が主となっています。基本的に社員とその家族が不安なく働ける環境を作ることを大切にしています。また、医療職にすべてを任せるのではなく、人事(会社)、上司、同僚が一体となって社員を支える体制を整えています。
さらに、両立支援は当事者にならないと、なかなか会社の制度や補助の仕組みに興味を持たないものです。そこで保健師からの提案もあり、当社オリジナルの「両立支援ガイドブック」を本人編・上司編と2種類を作りました。本人には制度の説明や職場復帰の仕方などを、上司には部下からの相談の対処の仕方や復帰後の対応方法などを周知しています。保健師などががん対策推進企業アクションなどの活動に参加し、他社の事例なども参考にしながら手作業で作ったもので、社員からもわかりやすくて良いとの好評も得ています。ガイドブックはいつでもwebで見られるようになっています。
また、2018年から実際に治療をしながら仕事をしている社員の体験談である「キラッとNOMURA Life~私の体験談~」をwebで公開しています。記事を見て相談にみえる方もいらっしゃいますし、「自分の体験も共有したい」という社員からの掲載希望も増えてきています。
がんという病気は、誰もが罹患する可能性がありますし、罹患した時のショックは普通の病気とは違うのではないかと感じています。そんな不安を解消するためにも、「キラッとNOMURA Life~私の体験談~」は、両立支援の風土醸成に役立っていると思います。
また、年次有給休暇を時間単位で取得できる制度があるため、抗がん剤などの通院時に利用することも可能になっています。
さらに、がんの早期発見につなげるため、2019年度より健保による「がん検診精密検査受診勧奨」も開始しています。「2人に1人ががんになる時代、早期発見・早期治療を行うことで働き続けることができる」というメッセージを伝えながら展開しています。「精密検査受診勧奨」と治療が必要になった方への「両立支援」の両輪を、健保と協力ながら推進していければと考えています。

--健康増進法の改正もあり、がん対策としての喫煙対策が各企業の中でも注目されています。野村證券では、どのような対策をされていますか?
社員の健康状態を可視化し、健康課題を把握するため「健康白書/健康カルテ」を毎年作成しています。その中から見えてきたのが「20代男性の喫煙率」の高さです。社員全体の喫煙率は20%程度で、ここ5年で2%ほど下がりましたが、20代男性は40%を超えています。このまま喫煙し続けると生活習慣病のリスクも高まってしまうので、今のうちに禁煙してもらいたいと考えています。
対策としては、健康増進法の改正以前から社内の喫煙所を徐々に減らしてきました。そして今年度から毎月22日を「スワンスワンの日」と設定して(数字の2がスワン【吸わん】に似ているから)、1日終日禁煙としました。
さらに、禁煙治療を受ける社員には今年度から治療費を全額健保が補助しています。
ちなみに、たばこを吸わない社員には健保のインセンティブ(健康ポイント)が付きます。
--現在のコロナ禍の中では働き方が変化していますが、社員の健康対策で変わってきているものはありますか?
在宅勤務のできる社員は、リモートが基本となっています。4月以降入社された社員や、人事異動などで新しい環境になった社員は、部署に慣れないうちからの在宅勤務でコミュニケーションが取りづらくなっています。
また、コロナも不安なのですが、もともと生活習慣病を持っている社員がコロナ禍の中で病院へ行きたくない、あるいは行きづらいとか、がんの治療が早期に行えないなどの問題点も出てくるかもしれません。そして、在宅勤務での運動不足などで体調管理も難しくなっているのではないかと思います。コロナ以外にも自分の健康に目を向けることが大切だと思います。
メンタルヘルスについても働き方が大きく変化していますので、心の健康を保ちながら生産性を持って働き続けられるような、今までとは違うケアが必要ではないかと手探り状態ではありますが考えているところです。
--今後力を入れていきたい健康対策は何かありますか?
がんや両立支援に関しての制度づくりは、作れるものは作ってきたと感じています。あとは、それが根付いていく環境をつくっていくことが大切です。医療職が社員に対してがんや両立支援に関する情報を積極的に発信したり、管理職が集まる研修などで周知徹底をしていきたいと考えています。今はコロナ禍ですので、メールやwebを活用していくつもりです。
また、現在は在宅勤務をしている社員も多く、職場で上司が部下を見守ることができづらいので、これまでのベーシックなメンタルヘルス対策だけでは済まなくなってきていると感じています。新しいメンタルケアが課題だと思います。
--ありがとうございました。
| 野村證券株式会社 概要 |
|