2024/12/27
令和6年度「がん検診受診率向上推進全国大会」を開催しました
(ページの最終更新日:2024年12月27日)
今年度は東京都港区虎ノ門ニッショーホールにて、
WEB配信を併用したハイブリッド形式にて全国大会を開催しました。
【主催者挨拶・国のがん対策の現状について】
九十九 悠太 氏(厚生労働省 健康・生活衛生局 がん・疾病対策課
がん対策推進官)

九十九 悠太 氏
我が国におきましては、2人に1人ががんにかかる状況で、がん患者の3人に1人は働く世代の方です。そのため皆様それぞれががん検診を受け、早期発見、早期治療に繋げることが非常に有効です。しかし、我が国のがん検診の受診率は、目標としている受診率60%を達成できていない状況です。この受診率を向上させられるよう、国としてもがん対策推進企業アクションの推進に努めております。2009年にスタートし、推進パートナー数は約5,500社を数えるまでに成長しておりますことに、関係者の皆様に厚く御礼を申し上げます。
最後にお集まりの皆様の今後ますますのご発展ご健勝をお祈りいたしまして、私のご挨拶とさせていただきます。
◆現在のがん対策の状況
がんとは遺伝子変異によりできるもので、血管などを介して体のあちこちに転移をきたす腫瘍を『がん』『悪性腫瘍』と一般的に言います。主な要因としてはやはり受動喫煙を含む喫煙、過度の飲酒、塩分の摂り過ぎなどの食生活。太りすぎ痩せすぎ、運動不足、ウイルスや細菌の感染が挙げられます。日本でがんになる人は年間約95万人、死亡者数は年間約40万人と言われています。現在は4人に1人ががんで死亡する時代で、日本の死因1位ががんです。年齢調整の死亡率というのは年々下がっており、生活習慣病の変化、また検診等の影響により従来多かった胃がんは非常に減少しています。
平成18年にできたがん対策基本法に基づくがん対策推進基本計画は、1期から数えて今回第4期が令和5年3月に閣議決定されました。がん予防、がん医療、がんとの共生の3つの柱となっています。がん検診の種類は主に対策型検診と任意型検診があり、政策で行っているのは対策型検診で、国が推奨している検診は胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん、大腸がん検診です。子宮頸がん検診はこの4月から、HPV検査単独法が新たに加わりました。
がん検診の受診率は上がってきていますが、なかなか半分を超えないものもあり、引き続き目標の60%を目指す状況です。
がん検診受診者の約3割から5割が職場、職域で検診を受診しており、がん検診未受診の理由について、受ける時間がないという回答が3割程います。
がんの医療は大きく変化をしており、2020年には平均入院日数は19.6日とかなり少なくなってきています。その半面、がんの患者数は増えています。実際はがん患者の3人に1人が20代から60代という働く世代です。仕事をしながら通院する方が約50万人います。70歳以上でがんに罹患している方が、2016年のデータと比較して令和4年で約2倍になっています。
がん診断後の就労への影響について、診断時に収入のある仕事をしていた人は44%、がん診断後に退職・廃業した人が就業者の約20%を占めており、そのうち初回治療までに退職・廃業した人が約6割もいます。再就職・復職の希望があるが無職の人が約20%という状況です。
国としましては、主治医や会社産業医、また両支援コーディネートのトライアングル型のサポートを提唱しています。がん治療後の生存率が医療の進歩等により伸びてきていますが、その一方で長期間にわたる療養が必要な人も増えていますので、長期療養者の就職支援事業も行っています。その他の取り組みとしまして、治療と仕事の両立支援ガイドラインというものを定めており、事業者、事業場における取り組み事項をまとめたものがございます。
最後になりますが、がん患者様が治療と仕事を両立しやすい環境整備、がんと診断されたときから相談できる環境整備、離職しても再就職について専門的に相談できる環境整備、このようなことを引き続き進めていきたいと思っています。私からは以上でございます。
【東京都知事ビデオメッセージ】
東京都 小池 百合子 知事
小池 百合子 知事よりメッセージをいただきました。
【がん対策推進企業アクション事業説明】
がん対策推進企業アクション事務局長 山田 浩章 氏

がん対策推進企業アクションは、職域においてがん対策を進めていくというプロジェクトです。本事業の開始から16年が経過し、現段階で約5,500のパートナー様にご登録をいただいており、大きく3つの施策を主軸として活動をしています。ひとつは、がん検診の受診を啓発すること。それからがんについて会社全体で正しく知ること。そして、がんになっても、働き続けられる環境を作ることです。
本事業ではパートナー企業様に向けた様々なコンテンツをご用意しています。中川先生のYouTube動画のほか、企業のがん教育に役立つe-ラーニングや小冊子の配布などがあります。本日のようなイベントも全て無料でご参加いただけますし、パートナー企業様の事例紹介などもしております。
それから大きく3つほど、パートナー企業様との活動もしております。ひとつが企業コンソーシアムという活動です。国や自治体の決め事だけではなく、実際の企業がどのようにがん対策を進めていくのかを企業様同士で話し合い、新しい事例を共有しています。2つめは、大同生命様と共同し、中小企業約7,000社~8,000社規模でのアンケート調査を行っています。中小企業の経営者ががん対策に関心があるかもがん検診の受診率に相関していることもわかっていますので、経営者に対する啓発を中心に行っています。最後はWorking
RIBBONです。子宮頸がん、乳がんという女性の特有がんに特化して対策をどう進めていくのかということを研究しながら啓発しています。
企業アクションへの登録自体は無料ですし、ご加入後も全て無料でご利用いただけるサービスですので、まだご登録されていない方はぜひご参加をご検討いただければと思います。ご清聴ありがとうございました。
【働く人に知ってほしい「がんのすべて」】
東京大学大学院医学系研究科 総合放射線腫瘍学講座 特任教授 中川 恵一
氏
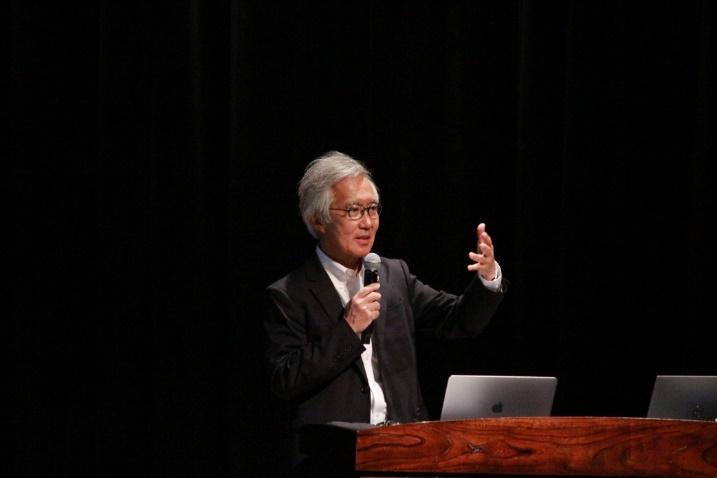
がんという病気は、知ることによって克服できる病気です。例えば男性の場合、生活習慣が良くなればがんのリスクは半分近くまで下がります。がんは早期発見できれば9割方治るという、制御可能な病気です。学校でがんの教育が始まっていますが、学校で学べない大人にがんのことを伝える、職場でがんのことを学べる環境を作っていく必要があります。ヘルスリテラシーを国際比較した研究があり、日本は最下位です。
◆両立支援を望める環境整備を
2000年のデータで、専属産業医がいる大企業に勤めるサラリーマンの死因の49.1%ががんで、今はさらに数値が増えています。新規のがん患者さんの3割が、働く世代です。重要なことは、がんという病気の最大の特徴は症状を出さないことです。早期に見つけるということが、がんの両立支援の根本です。
しかし、がんと告知されたらその場で治療法を決断しないことです。標準治療を選ぶ、簡単に言うと保険で認められている治療しか受けないということです。自由診療に手を出すことは基本的にはしない。また仕事を辞めないことも非常に重要で、本人だけではなく、職場として仕事を辞めさせないことです。そしてセカンドオピニオンをすること。
特に進行がんの場合は両立支援が非常に重要で、一定の困難を伴いますが、患者本人が両立支援を受けたいと言うことです。社員ががんにり患したことを本人の同意なしに職場が知ることは、法律違反です。したがって、両立支援を受けたいと言える環境、言える会社であることがとても大事です。両立支援については、時間単位の時短勤務を許容することが、両立支援をする上で最も重要だと経験者が語っています。
◆放射線治療の有効性
放射線治療は完治に繋がらないという理解が日本人に多く見られますが、10年後の生存率は外科手術と同等です。治療後の生活の質は圧倒的に放射線の方が良いです。前立腺がん患者のある例ですと、おおよそ6分30秒で1回の放射線治療が終わり、こちらを5回繰り返すだけで、入院をして全身麻酔をかける手術と同じ治癒率になります。
そして放射線治療は99.5%保険が効きます。医療費は先ほどの5回の治療で63万円、3割負担で19万円です。保険が効くということは高額医療費制度が使えるので、一般的な所得のサラリーマンは9万円で済みます。両立支援をする上で放射線治療は非常に有力なので、知っていること、あるいは職場でも勧められることが大切になります。手術と言われることも多いので、セカンドオピニオンを勧めましょう。
◆がんを防ぐ生活習慣
がんは遺伝子の老化で、年齢とともにできるがんの遺伝子数は60歳でおおよそ5,000個とも言われています。がんは運の要素も強く、自然に発生します。遺伝子の経年劣化に伴い、どんなに良い生活習慣でもがんはできる可能性があります。そして免疫力も年齢とともに衰えます。たった一つのがん細胞が2個に分裂し、それぞれがさらに2個に分裂する。8個、16個、32個、64個と増えていき、30回分裂すると2の30乗で10億個となり、20年かけて約1センチになります。早期がんとは2cm程度のものを指しますが、1cmにならないと我々のような専門医でも見つけられません。1cmから2cmが発見可能な早期がんになります。2cmになるまでは1年から2年になります。そのため多くの住民検診は2年に1度、肺がんなど早いものは毎年受けることを勧めています。
がんに備える基本は非常にシンプルで、がんに罹患しないような生活習慣がひとつ。そしてもうひとつ、運の要素も非常に大きいため、運悪くがんに罹患した場合は早期に見つけることです。
生活習慣の話は皆さんもよくご存じかと思いますが、タバコを吸わないことです。受動喫煙でも肺がんは3割増えますし、今のご時世はお酒もゼロがベストとなっています。細菌やウイルス感染も非常に重要です。胃がんはピロリ菌、子宮頸がんはヒトパピローマウイルス、そして肝臓がんはC型B型の肝炎ウイルスが7割程です。また、長時間座っているとがんが増えることも知るべきです。あまり座らない方に比べて82%がんの死亡リスクが増えますので、ある意味タバコ以上です。運動不足とは違い、太ももの筋肉を動かさないことが非常に大きなリスクです。
◆5つのがん検診受診が基本
住民検診では胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がん検診がありますが、これらは健康増進法という法律が裏付けになっており、これらの検査を受けていただくことで、がんによる死亡が減るというデータもあります。がん検診は職場で受けることが多いため、職域における検診は非常に重要です。子宮頸がんについては、5年に1度のHPV検査単独法が今年度より新たに指針の中に加わりましたが、会社での実施は非常に難しいのではないかと思います。
合理的な範囲で考えていただく必要があり、職域で対策型検診を実施することが基本です。
中小企業の社員は基本的に協会けんぽに加入しますが、こちらの生活習慣病予防健診が基本的ながん検診をカバーしています。乳がんと子宮頸がんがオプションなのは気になりますが、こちらを受けていただければ概ね事足ります。令和5年から自己負担も非常に安くなっており、約5,000円で受けることが可能です。協会けんぽの生活習慣病予防健診を実施し、プラス女性の乳がん、子宮頸がんのオプション費用も会社に負担していただければ事足ります。
住民検診は法律の裏付けがありますから受診勧奨ができます。しかし、職域でのがん検診は法律の裏付けがないので「あなた精密検査で陽性でした」と会社側が伝えることができないのです。したがって、そうした際に伝えることへの同意を得ることが肝要です。
◆女性特有のがんは若い世代も罹患
女性は若い頃からがんになるということも非常に重要です。働く人ががんになる数は、55歳までは女性の方が多いです。これは女性の方は老化とは関係のない要因、乳がんと子宮頸がんがあるからです。子宮頸がんは性交渉によるHPVウイルス感染が原因のほぼ100%で、性的に最も活発な時期に感染したウイルスが30代後半あたりにピークを作ってきます。乳がんはピークが2つ、そのひとつは女性ホルモンの分泌が止まる前の40代後半です。子宮頸がんは30代の後半にピークがあり、ヒトパピローマウイルスの影響ということになります。
今、HPVワクチンが小6から高1の女子に対して無料で接種できる法改正がされています。子宮頸がんの発症リスクが1割程度にまで減らせます。しかし日本では副反応をめぐる報道などにより、8割あった接種率が一次はゼロになり、今も正式な接種率は出ていないようですが、おそらく1~2割です。このHPVワクチンは小6から高1が法定接種なのですが、積極的な勧奨を控えた平成9年から平成19年までの11学年の方に関しては大人では法定接種の対象年齢ではなくとも、当面無料のキャッチアップ接種が行われています。
◆大人のがん教育の課題
働く世代、特に高齢男性と若い女性にがんが増えるという問題、それを私はがん社会と呼んでいます。単一民族である日本は社会成熟すれば、少子化が進むわけです。結局高齢者が働くしかないわけです。経済成長も社会保障制度の維持もままならないというわけで、日本は70歳過ぎても皆さん働いています。年金の支給開始年齢が70歳にならないと破綻します。皆が定年まで働けば会社員の5人に1人ががんになると見られます。
他の先進国では、学校でがんのことを習うのは当たり前です。日本でもようやく中学校と高校で習い始めて、法律の裏付けのある体制型検診を受けましょうと中学生は学びます。あるいは、高校になれば放射線治療についても学びます。ですので、大人のがん教育が重要で、企業アクションのミッション・課題に職場でのがん教育、とりわけ経営者へのがん教育を掲げています。特に中小企業の経営者の方にがんに関して知ってもらうことが、非常に重要なミッションかなと思います。そして今健康経営でないと採用も非常に難しく、離職も増えます。がん対策は経営課題です。あまり知られていませんが、改正されたがん対策基本法、ここでは企業でのがん対策は事業主の責務になっています。
ご清聴いただきましてありがとうございました。
【トークセッション】
中川 恵一 氏、大西 幸子 氏、久家 麻美 氏、後藤 英子 氏


第2部でご講演いただいた講師のみなさまと中川先生でトークセッションを行いました。
がん予防の重要性について議論され、がん検診の低受診率の課題も指摘されました。「NBM(ナラティブベースドメディスン)」を活用した感情に訴える啓発や、伝わりやすい案内作成の必要性が強調され、教育や意識改革の重要性も議論されました。