2025/10/01
令和7年度 メディアセミナー開催報告
<メディアセミナー開催概要>
5年生存率1割の最凶がん(すい臓がん)にどう備える?
開催日時:2025年8月27日(水) 13:00~15:30
開催形式:会場とオンラインのハイブリッド形式
会場:星陵会館ホール
がん対策推進企業アクション(厚生労働省委託事業)は、2025年8月27日(水)にメディア向けセミナーを、会場とオンラインで同時開催しました。
当日は死亡率8割超のサイレントキラーとも呼ばれるすい臓がんについてどう備えるか、がん対策推進企業アクションの議長であり、がんの緩和ケアに係る部会の座長も務める中川恵一先生(東京大学大学院医学系研究科 総合放射線腫瘍学講座 特任教授)による講演のほか、株式会社シンク・アイホールディングス 代表取締役社長・CEO京谷忠幸氏による講演やトークセッションが行われました。
<5年生存率1割の最凶がん(すい臓がん)にどう備える?>
東京大学大学院医学系研究科 総合放射線腫瘍学講座 特任教授 中川恵一氏
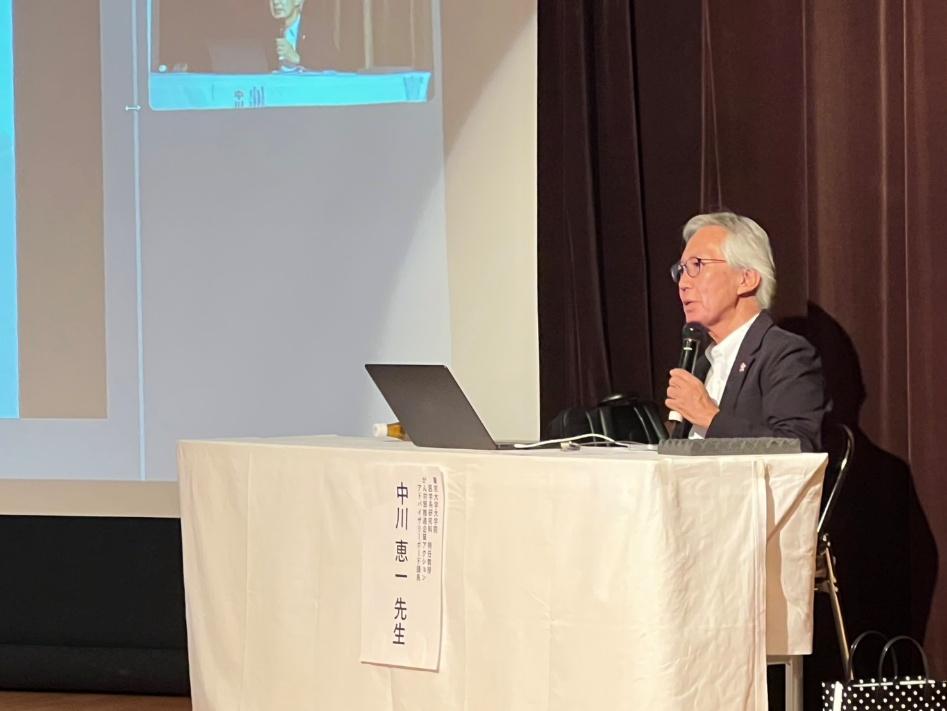
がん種別に5年生存率を見たときに異様に低いのがすい臓がんで、すい臓がんの死亡数は罹患数とほぼ同じです。4万5,000人が罹患し4万人以上が死ぬ、5年相対生存率は8.5%というデータがあります。
■すい臓がんとは
すい臓は十二指腸に隣接していて、すい液を出します。インスリンなどのホルモンも血管の中に放出します。すい臓は、膵頭部、膵体部、膵尾部の3つに分かれており、膵頭部が最も手術が難しいです。膵頭部のがんは十二指腸と胆管を取ることになり、食物の通り道がなくなるので、複雑な再建が必要になります。患者数は、がんの中では決して多いわけではありませんが、死亡数のランキングになると男性では4位、女性では3位、全体では3位になります。しかし、国が推奨するがん検診の中にないという問題があります。
■近年での罹患者数増加と生存率
すい臓がんはこの20年で罹患数、死亡者数がともに2倍に増加しています。理由として非常に重要なのが糖尿病です。糖尿病はがんのリスクを平均で2割程度増やし、特にすい臓がんや肝臓がんではリスクが2倍になります。血糖値、特にヘモグロビンA1cの2ヶ月平均が理由なく上がるとき、すい臓がんが関与することが相当あります。生存率は全ステージの平均で8~9%、ステージ1でも4割程度です。そのため、ステージ1になる前の上皮内がん、あるいは遅くても1cm以内で見つけることが重要です。すい臓がんは手術が標準治療であり、手術できるかどうかが重要なポイントです。しかし、発見が遅れることが多く、症状も出にくいため、症状が出た時にはすでに手術が難しい。さらに、血管への浸潤や転移の進行が早いことも大きな問題です。そのため、最近では手術の前に抗がん剤を使ってがんを小さくし、手術不能を手術可能とする、「コンバージョン手術」が実施されています。
■なぜ対策型検診の対象とならないか
すい臓がんが対策型検診の対象とならない理由の1つとして、かんたんな検査が存在しないことが挙げられます。超音波検査では膵頭部は見ることができますが、膵尾部まで見ることはできません。すい臓がんは1cm未満で発見できれば9割は治りますが、7割が手術不能です。すい臓がんの多くは遠隔転移しており、限局している割合は5~6%程度です。つまり、細胞分裂のペースが主要がんの中で最も早く、診断が難しい。すい臓がんを見つける所見としては、IPMNなど、嚢胞が大きくなっている場合にすい臓がんを疑う必要があります。そのほか、すい管の拡張や途絶、くびれができることも同様です。多くのがんが1~2cmになるのに1~2年かかるところが、すい臓がんだとおよそ3~6か月です。そのため、すい臓がんに関しては、検診が年に1回では間に合いません。これもすい臓がんが対策型検診にならない大きな理由のひとつです。
■すい臓がんの最新放射線治療とは
すい臓がんはピンポイント照射である「定位放射線治療」が手術不能例に対して保険でも認められています。南東北がん陽子線治療センターの症例で言いますと、放射線治療用吸収性組織スペーサーを使用し、従来と比べ1回あたりはるかに高い線量(4グレイ)を20回に分けて実施する特殊な治療をしています。これにより1年局所制御率が100%で、重度の有害事象はゼロを実現しています。まだ1~2年の観察なので5年生存率がどれだけになるかわかりませんが、有望な方法です。
もうひとつご紹介したいのは、MRリニアック(MRI+放射線治療装置)を使った放射線治療です。放射線治療は高精度化していますが、その肝となる部分は治療装置そのものを使って画像を撮り、高精度に放射線を照射するというものです。しかしMRリニアックは日本で3台程度しか導入されていません。一般的なリニアックでは、治療用ビームと同時にCT用のX線が出て、画像化します。それに対して、MRリニアックは被ばくがなくリアルタイムで可視化でき、画質にも優れますので、特にすい臓がんはMRリニアックがないと治療できません。残念ながら、診療報酬や導入コスト面での問題で、普及が難しいという課題があります。
<すい臓がん経験者による講演>
株式会社シンク・アイホールディングス 代表取締役社長 CEO 京谷忠幸氏

私は1962年生まれで63歳です。父は私が9歳のときに胃がんになり、享年37歳でした。母親は、私が中学2年のときに末期の十二指腸がんになり、私が16歳のときに享年40歳で亡くなりました。両親ともすごく働き者でしたし、概ね50年ほど前の話になりますので、健康リテラシーについて考える機会は全くなかったのかもしれません。
今、私にも子どもが3人おりまして、孫もおります。遺伝的なことはあるのだろうなという思いはありましたが、すい臓がんについては全く意識がありませんでしたし、どう注意をしたらいいのか全く見当がつきませんでした。自分が大病しましたので、子孫のためにもどうやって健康リテラシー向上を図るか、それを家訓として残したいですし、遺伝子検査をきちんとやりたいという思いがあります。かつて奨学金や生活保護で助けられてきました御恩があるので、企業代表者としてお手伝いしたいと思います。
■違和感があっても検査は異常なし
これまで福岡の病院と東京の病院で定期的に人間ドック・PET検査を実施してきました。膵臓がん発覚の半年前にはPET検査ドック異常なしと診断されていたんで、がんを疑っていませんでした。
それで2022年6月になんとなく違和感があり、東京のクリニックで血液検査を受けています。コロナも疑いましたが、ここでも異常はありませんでした。10月に東京で胃カメラをしましたが異常なし、このときもすい臓がんは心配しておりませんでした。ストレスが多い立場でもあるのですが、胃腸薬を飲んでもすっきりせず、しかも痛みもなく違和感だけでしたが、念のためと福岡に戻ってかかりつけ医の先生に相談して行った検査も腫瘍マーカーは反応していません。それで次に一応エコー検査をしましょうとなり、膵管の拡張が少し見えたということで精密検査をしたくて受診できる大学病院を幾つも探しました。
■急性膵炎での入院からがんの疑い
そうした経験をしてきて私が感じるのは、これまでと比較するためにも、同じ病院で検査をすることは必須だと思います。ただ、かかりつけ医がそこまで高度な検査ができるかはわかりません。その一方で、地域で少し相談できるところは絶対必要だとも感じます。それと、画像で経過観察ができるということは、特にすい臓がんにおいては必須だと実感しています。
東京の大学病院で検査しましたが、最初は紹介状がなく、高い異常データではないと判断されて受け付けてくれませんでした。自費だといいですと、探し当てた大学病院を受診したところ、急性膵炎という所見で入院しました。入院中の精密検査で膵臓がんが分かり、大きさとしては15ミリほどでした。その時は標準治療が術前抗がん剤と言われましたが、副作用で40度ほどの熱が出ています。入院中にがんの疑いがあると言われまして。EUS(超音波内視鏡検査)も細胞摂取によって膵炎が起こるリスクがあり、がんであれば数%の確率で医療事故の危険性もあります。
すい臓がんで亡くなったスティーブ・ジョブス氏は手記に「東洋医学に偏っていましたが、最初に手術すればよかった」とあり、なおかつ千代の富士も星野仙一監督も、あれだけ体力のある方が瞬く間に亡くなったと知り、危機感を持ったという経過です。最終的に超音波内視鏡と生体検査をして、がんが見つかりました。
また、膵頭十二指腸切除と再建手術で、手術は大変難しくリスクもあると聞いて手術実績の多い大学病院へ転院して手術は成功しました。
■付加検診で従業員のすい臓がんを発見
従業員を多く抱えている中で、私自身ががんサバイバーになりました。親のがんによる遺伝もあり、人生がすべて計画通りになるものではありません。人生がままならず、祖母に育てられました。親が早世すれば人生計画は狂い、何も選択できなかったという思いもあります。だからこそ今、企業経営者として働く従業員を守りたいと思っています。従業員に健康知識を発信し、がん対策推進企業アクションの冊子も配りました。社内も一般検診のみではなく付加検診で各腫瘍マーカーや、女性の付加検診、その他もずっと会社として実施してきたところ、結果的に働く人たちの意識が上がりました。そして社員に2人、すい臓がんが見つかりました。ひとりは早期で、40代女性でしたが涙ながらに感謝してくれました。もうひとりはステージ4で2か所転移していましたが、最初は何の違和感もなく普段通りの生活をしていました。健康意識が上がると、健康をどう作るかという考動にもつながり、未病対策にもなります。
■企業経営者として知識と情報を広める
企業経営も難しくなる今、経営者側は「指示」ができますので、一般検診の他に付加検診を組み込むことが肝要です。もうひとつ、昨今は健康経営が標榜されていますが、この健康経営の中にがんや健康リテラシーについて明言されていません。
私どものグループウェアでも、このがん対策推進企業アクションをどんどんコマーシャルしております。中川先生の日経新聞『がん社会を診る』の記事も素晴らしい内容なので、こちらもグループウェア内で配信しています。私も様々な団体に関わり要職を仰せつかっていますが、がんについてや健康リテラシーの情報が全然入ってこないのです。知識や情報にアクセスできることをしなければもったいないと思います。ぜひメディアのみなさまにご協力いただきたいです。